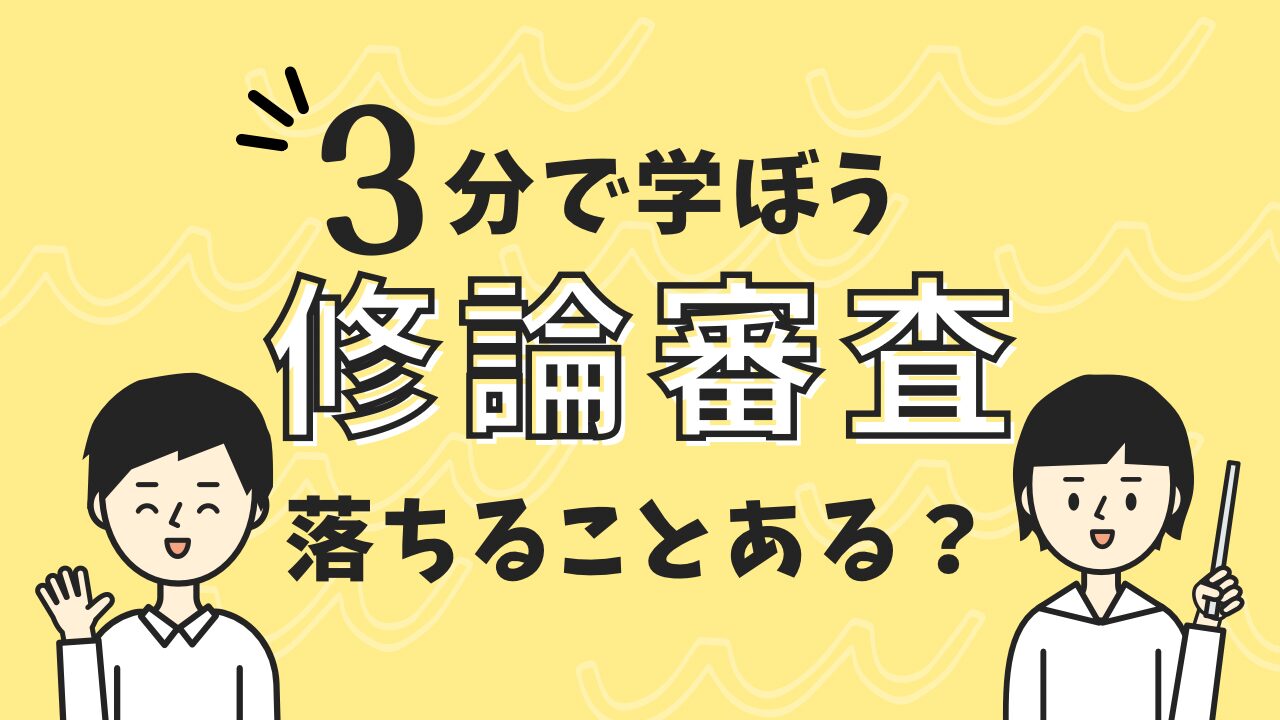修論や卒論の審査に向けて、準備は進んでいますか?
私かるびは、修論の準備をサボっていたせいで、それはそれは大変な思いをしながらなんとか卒業しました。
社会人の今より圧倒的に労働してた…
この記事を見つけたあなたはきっと、私のように激焦りをしていることでしょう。
そこで本記事では、実体験をもとに修論審査に土壇場で間に合わせるにはどうしたらいいのかを解説していきます!
修論審査の流れ

まずは大筋を確認しておきましょう。
専攻ごとに詳細は異なりますが、おおよそこの流れに沿っていくはずです。
・12月中旬〜1月上旬: 初稿提出
・1月上旬〜2月上旬: 修論審査
・2月上旬〜2月下旬: 最終稿提出
審査の際には初稿提出から修正・追加したい内容を差し替える事ができます。
最低限、初稿さえ提出できれば、なんとかなるもんですよ。
修論審査で落ちることはある?
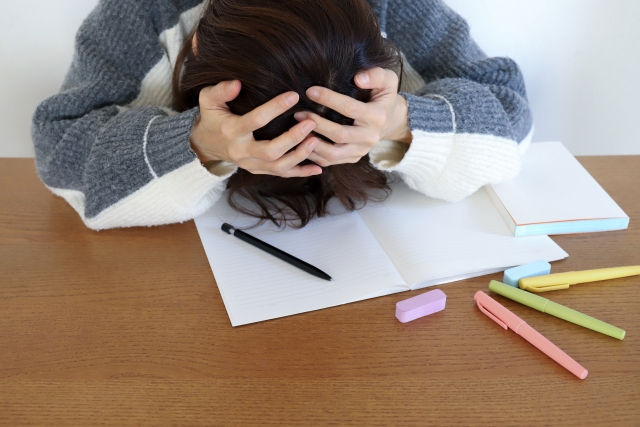
結論から申し上げれば、落ちることはあります。
しかしながら、早々あり得る話ではありません。
研究者を真剣に育成する校風なのかにもよりますが、基本的に審査は優しいです。
修士を卒業後に企業就職を選ぶ人が7割を超えることからも、卒業はさせようと考えてくれています。
とはいえ、安心せず今すぐに研究に力を注ぐようにしましょう。
【3選】修論審査で落ちる人の特徴
完全に主観ですが、以下の3点を満たしている人は本当に落ちている印象があります。
というか、審査のために論文を書くスタートラインにすら立てません。
- 研究室に全く来ていない
- 指導教員とコミュニケーションを取らない
- 提出2ヶ月前になっても、本当に一切のデータがない
私の知る限り、この3点を満たしている先輩や同期はもれなく留年・除籍を喰らっていました。
一つでも改善されていれば、あとは指導教員に泣きつくなり先輩のデータをもらうなりで卒業はできることもありますよ。
【3選】修論審査なんとかなる人の特徴
これも私の主観ですが、意外となんとかなる人が持ち合わせている特徴です。
- 当初の予定通りのデータがとれていない
- 実験だけはちょっとでもやってる
- 指導教員と会話はしている
修論審査にあたり、一番まずいのが初稿提出直前になっても一つもデータがない状態です。
予想と異なろうとデータさえあれば、考察はなんとでも書けるため、審査を突破できる可能性が飛躍的に高まります。
そのため、焦っている人は今すぐ1つでもデータを取っておきましょう。
【体験談】かるびのカス修論

私自身、カスみたいな修論を提出し、なんとか卒業することができました。
本記事を読んでくださっている皆様には同じ轍を踏んでいただきたくありません。
私の場合、就活に時間を割きすぎて失敗してしまいました。
インターンには6月から本選考まで20日以上参加し、その上で参加できる座談会には全て出席。
当時は研究職に就く予定はなく、研究には時間を割いていられないと思っていたんです。
そのせいで夏の就活が本格化する頃から徐々に研究室に行かなくなり、実験頻度が下がっていってしまいました。
気づけば12月。
完成した修論から考えると、全Figureの1/7までしか進んでいないカスみたいな進捗で、指導教員からも心配される有様でした…。
いつから本気を出して間に合った?
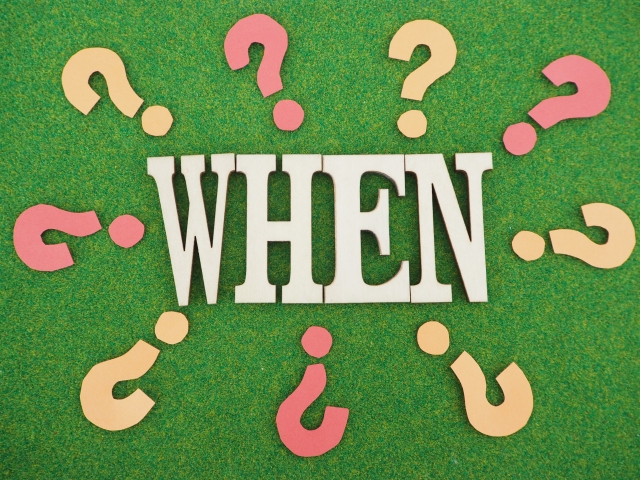
僕が実験に集中し始めたのは就活も終わりかけの5月頭から。
幸いにして、生物系の中でも細胞を扱う実験系をメインにしていたため、実験のサイクルは短期間でぶんぶん回していけました。
朝10時に研究室にいき、夜11時に帰る生活を11月まで続け、なんとかデータを回収することに。
細胞が予定通りの挙動をしなかった時、使っていた2000万のカメラが動かなくなった時。
本当に終わったかと思いましたが、都度都度軌道修正をし、なんとか完成まで漕ぎ着けることができました。
研究を頑張ってるやつほど、いいところに就職する
終わってみてから気づきましたが、研究を頑張っていた人ほどいいところに就職しています。
インターンにどれだけ参加したかなんて関係ありません。
しっかり研究ができる修士生ほど、論理的思考力、俯瞰力、行動力に突出しています。
しかも、「学生時代、研究を頑張った」という確固たる実績と経験さえあれば、いくらでも面接で勝負できるようです。
私のように打算と浅い計算で動く人間は、人事からも見透かされてしまうようですね。
修論審査に間に合わせるには
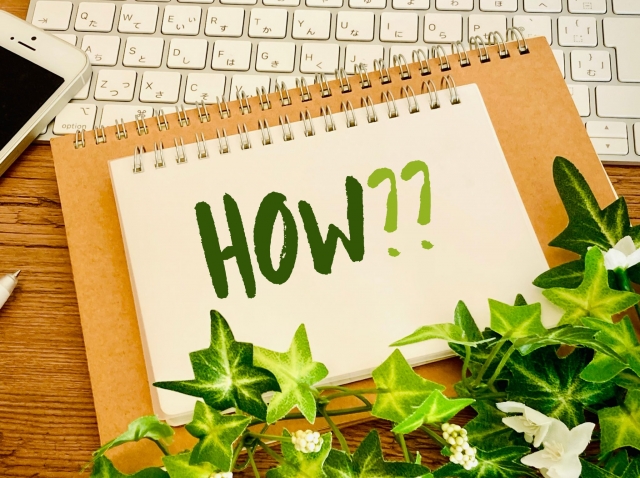
結論から逆算して最短ルートで
修論•卒論は結果が伴わなくとも、ストーリーさえ描けていればまとめることができます。
この記事をわざわざ見ているということは、きっとあなたに残された時間は短いはず。
1月単位の大雑把な計画でも構わないので、実験計画を建てて全体像を把握しておきましょう。
死なないから死ぬ気で時間をかける
あとは単純、死ぬ気でデータをとるだけです。
材料は沢山あるに越したことがありません。
書き始めると意外とデータ同士の繋がりが見えてきて、新たな考察が生まれるものです。
一例ですが、私はqPCRの待ち時間で細胞の継代や組織染色、FACSを1日で行っていました。
不安に思う時間があるなら即行動しましょう!
【結論】今すぐ行動しよう!
いかがでしたか?
今の日本において、正直修論•卒論は就活が終わった後の半年で一気に仕上げるもの。
先輩方で上手くいっている人はごく稀です。
焦らず、冷静に即行動していきましょう!