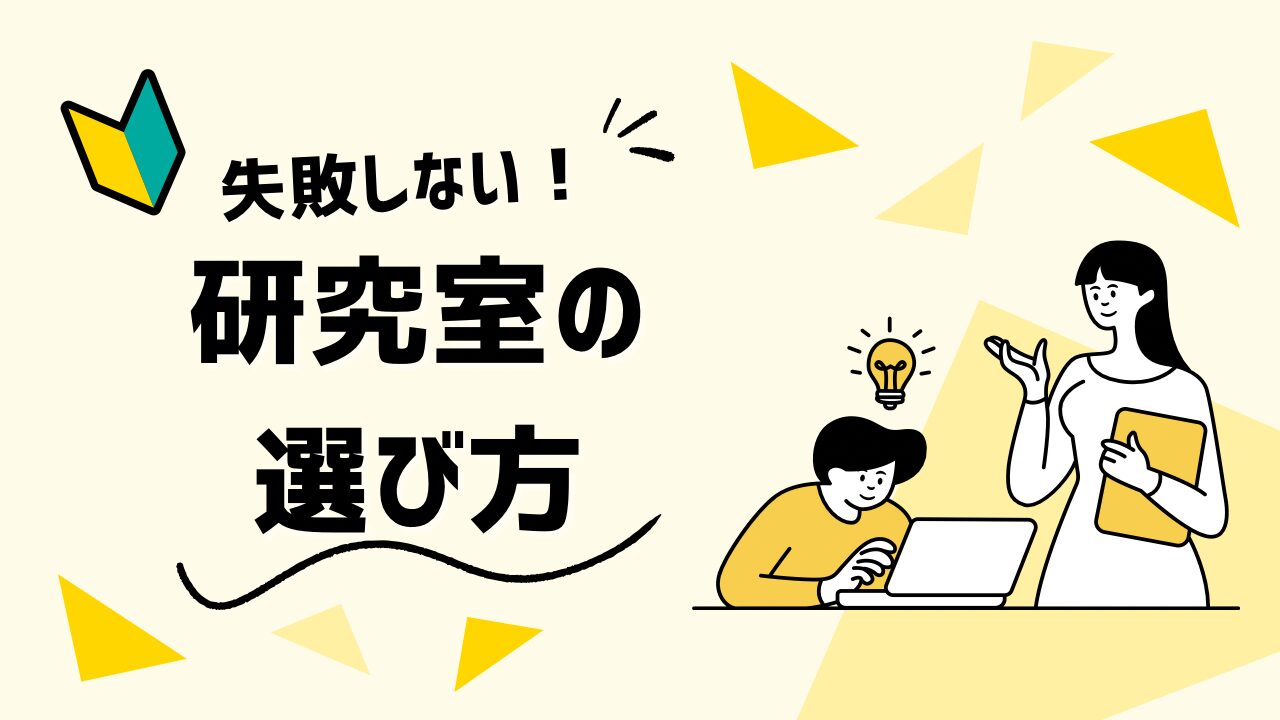大学3年生や修士1年の皆さん、「どの研究室を選べばいいか分からない」と悩んでいませんか?
研究室選びは、就職・進学・大学生活そのものに直結する、超重要な選択です。
とはいえ
- 研究テーマに興味持てるのか?
- 雰囲気はどう調べる?
- ブラック研究室は避けたいな
と、判断材料に困るのが現実ですよね。
僕もとんでもなく悩んだな…
この記事では、理系学部生が失敗しない研究室の選び方を、わかりやすく解説します!
「なんとなく」で研究室を決めるのは危険です。この記事を読んで、納得できる選択をしましょう!
【結論】ホワイト✖️実績✖️人間関係で選べ
結論から申し上げれば、以下の3点が重要なチェックポイントです。
- 休みが取りやすいホワイト環境か
- 修士・博士の学会参加・論文数は?
- 人間関係は良好か
もう少し詳しく解説していくよ!
研究室の情報を得るためには?

研究室選びのためには、情報を入手して行く必要がありますよね。
基本は口コミと研究室見学
基本的に口コミとHPで粗く探し、研究室見学で情報を入手していきます。
情報は生に近く、信頼できることが鉄則です。
- 大学から研究室リストが配布される
- 研究室のHPで探す
- 先輩・同期に口コミを聞く
- 研究室見学に向かう
自分でコンタクトを取れば、大学1年生からでも研究体験をさせてもらえます!
私は大学3年の春から3つくらい回ったかな〜
学位をもらえる研究室かどうか、確認は必要ですが、期限に間に合えば早く動いても大丈夫です。
ぼっちで情報を得られる知り合いがいない時は?
大学は高校までより人間関係が希薄になりやすい環境ですよね。
安心してください。ぼっちでも十分良い研究室が見つけられます。
ぼっちであるデメリットは以下の通りだと考えられます。
- 手分けをして情報を集めにくい
- 有名なブラック研究室を探し始めに知りづらい
正直、このくらいです。
対策としては、とにかく研究室見学を申し込みまくること!
大体の研究室で年次の近い先輩と話す機会をいただけるので、そこで同期に聞くような話を伺えば問題ありません。(配属されなければ会わない先輩ですから、遠慮はいりませんよ😇)
研究室選びの本質は「自分にピッタリ合う環境を見出すこと」です。
どれだけ周りに聞きやすい人がいようとも、肌で感じなければ実になる情報は得られないものです。
安心して突貫していきましょう。
【5選】失敗しない、研究室選びの観点

研究内容と自分の興味の合致が最優先
研究内容が自分の興味と合っている研究室を選ぶことが、モチベーション維持の鍵になります。
なぜなら、大学院生活では長期間にわたって一つのテーマに取り組むため、興味が持てないと継続が困難だからです。
- 実験がつらくても「好き」で乗り切れる
- 自発的に論文を読むようになる
- 就活の軸になるかも
特に論文!興味がないとマジで自発的に読もうなんて思えない
研究の面白さは続ける力になります。興味関心は妥協せずに見極めましょう。
指導教員のスタイルと相性
指導教員の指導スタイルと自分の性格が合っているかは、研究室でのストレスを大きく減らします。
ストレスは研究の進捗に影響するだけでなく、進路指導や推薦にも支障が出るからです。
- 教員が放任主義か丁寧にしっかりか
- 先輩は話しかけやすそうな人が多いか
- 研究と就活のバランスが取れそうか
教授って変な人結構いるんだよね
研究室見学に行った時は、まず初めに確認しておきましょう。
研究室の雰囲気・人間関係が良好か
研究室内の人間関係は、精神的な安定や研究の効率に直結します。
長ければ10年近くいる研究室ですから、居心地が悪かったら最悪です。
見学やOB訪問で「空気」を感じ取り、自分にとって居心地のいい場所かを確認しましょう。
指導教員はもちろん、長く在籍している博士生の人柄にも注目して見ると良いかもしれません。
【実績】就職や修士までの学会参加・論文投稿数
卒業後に先輩がどこに就職しているのか、就活と研究のどちらを重視するのか確認もしておきましょう。
特に研究職に就きたい場合、テーマによって志望動機が書きやすくなることがあります。
- 大手メーカーに毎年推薦枠があるかも
- 博士進学率はどのくらいか
- 就活に理解があるか
個人的には就活に理解があるかどうかがマジで大事
中には、研究者になること以外認めないところもあるので、必ず選ぶようにしましょう。
また、研究職を目指すのであれば学会参加数や論文投稿数は特に重要になります。
ガクチカに研究力がある定量的な指標を出せるのは本当に強い。
研究職に就職した生物・ライフサイエンス・農学系の友人たちは最低限、修士卒業までに国内学会に1回は参加していました。
ウェットよりドライの方が実績を出しやすいため、テーマの観点を組み合わせるのも一つの手です。
コアタイムとミーティング頻度
研究室によってはコアタイムという、絶対に滞在していなければならない時間があったりします。
これがあるかないかで、研究室生活は大きく変わります。
- コアタイムの有無
- ミーティングの頻度
- 土日夜間は電気がついてる?
経験上、9-17コアタイム週2ミーティングまでは楽だったな
もちろんコアタイムがあれば、絶対にサボれない、質問に行きやすいと行ったメリットもあります。
自由度が大切なのか、自問自答してみてくださいね。
【個人的には】人間関係が神でコアタイムありな研究室がおすすめ
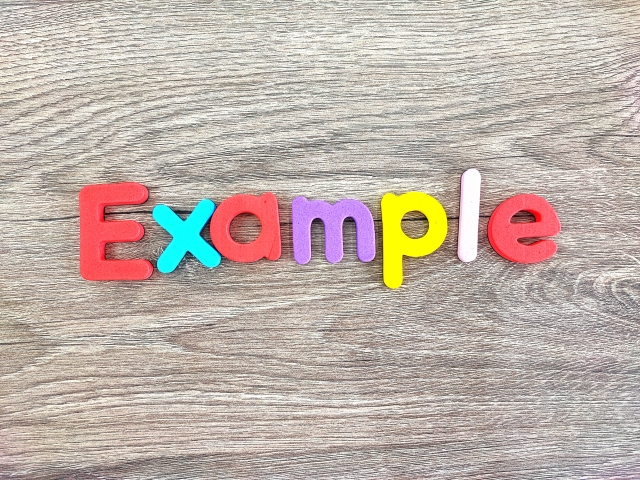
ここからは個人的な価値観になりますが…。
学部生の方で、遊びも頑張りたい方には人間関係を最優先に、コアタイムありな研究室をおススメします。
具体的には、
- コアタイムは9:00~1700
- 居場所を監視されない
- PR、JCの頻度は週2回
- 指導教員にいつ話しかけても丁寧に対応してくださる
- 1学年最低2人の先輩がいる
- 定期的に飲み会やパーティを開催
私がいた研究室がまさにこれでした。
コアタイムがあれば義務感で研究室に行くので、サボる気にならないんですよね。
また、研究が嫌いになる、研究室が嫌になる原因の多くは人間関係に起因しています。
例え実験がうまくいかない期間が続いても、話しかけやすい指導教員や先輩がいるだけで、すぐ軌道修正できるものです。
半年くらい実験が進まなかったことがあったけど、教授が毎日相談に乗ってくれたり、同期・先輩と愚痴を繰り返してでなんとか乗り切れたな~
また、数年間同じ部屋で毎日顔を突き合わせる人たちです。
そのため、コアタイムあり、人間関係最優先で確認していくのが本当におすすめです!
まとめ
いかがでしたか?
研究室選びは将来を決めかねない重大な選択です。
本記事を参考に、納得のいく選択をしてくださいね