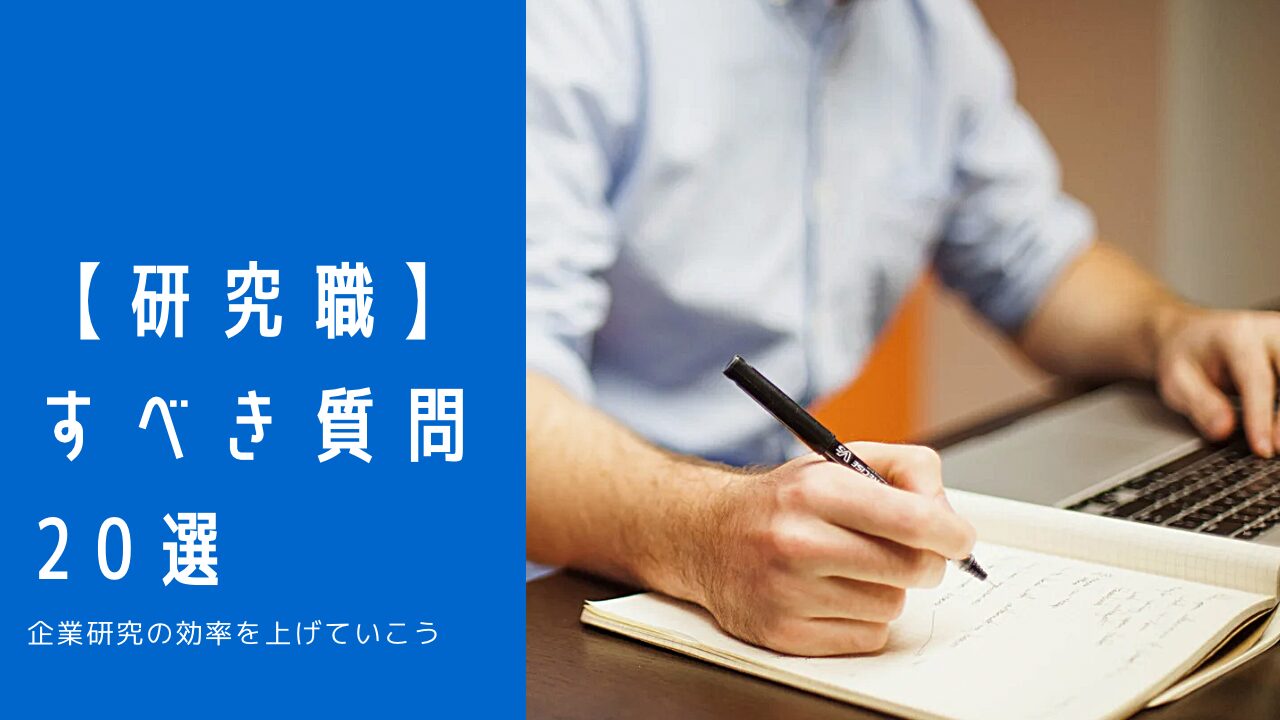こんにちは、かるびです。
本選考が始まると、説明会にESに面接にと多忙な日々が続きますよね。
並行して研究活動を進めるために、効率を求めたい方も多いはずです。
そこで、特に研究職志望の方向けに、先輩社員への質問例を解説していきます!
この記事を読めば、効率的に職種理解をするためのフォーマットが理解できますよ。
- 説明会・OB訪問での質問のコツ
- 人事と先輩社員に聞く質問は変える
- 【20選】説明会・OB訪問の質問例
- 研究テーマはどのように決定されますか?
- 研究成果を事業化するまでのプロセスを教えてください
- 1日の業務の流れを教えてください
- 研究職に求められるスキルや資質は何ですか?
- 新卒が1年目から3年目までに行う仕事はどのようなものですか?
- 社外研究機関との連携や出向はありますか?
- 企業研究とアカデミアの研究の違いは何ですか?
- 学会発表や論文投稿の機会はありますか?
- 研究テーマには裁量権を持って携われますか?
- 研究職のキャリアパスにはどのような選択肢がありますか?
- 研究職から別の職種にキャリアチェンジするならどのくらいの期間が必要ですか?
- 研究成果が出てからどの工程まで携わりますか?
- 開発部門や他部署との連携の仕事と実験の比率は?
- 研究テーマの変更や新規プロジェクトの参加はどのように決まりますか?
- 研究成果が評価される基準や指標は?
- AIやデータサイエンスを活用した研究への取り組みはありますか?
- 研究に失敗した時や難航した際の対応は?
- 在宅勤務はどのくらいできますか?
- 企業の成長戦略の中で、研究職が果たす役割は何ですか?
- 研究にかけられる予算や設備の充実度について教えてください
- まとめ
- 脚注
説明会・OB訪問での質問のコツ
まずは自分で質問を考えやすくするため、先輩社員への質問のコツについて解説して行きます。
目的を明確にする

一番は質問の目的を明確にすることです。
これは、意図のはっきりした質問ほど回答と自分が求める方向性に齟齬が少なくなりやすく、かつ回答者も答えやすいためです。
例えば、アバウトに「この仕事ってきついですか?」聞いてしまうと回答者には労働時間やメンタル、仕事内容故など様々な観点から答えを選ぶ手間をかけてしまいます。
自分が労働時間の長さにフォーカスを当てていた場合、ずれが生じることにもなりますよね。
そのため、観点を絞り込めるような自分の考えを冒頭で喋れると良いです。
❌ この仕事ってキツいですか?
⭕️ 多くの業務を並行することが苦手なのですが、そういった大変さはありますか?
同じ質問を他の企業でもする

毎回違う質問を他の企業ではしてしまいがちではありませんか?
同じ質問を他の企業でも行うことで、横の比較が容易になります。
そのために、自分が重視している観点を表にまとめ、他の人が聞かなかった部分を埋めるように質問を考えていきましょう。
自分が同業他社に比べてどこに魅力を感じているのか明確になり、志望動機の作成が後々非常に楽になりますよ。
人事と先輩社員に聞く質問は変える

人事と先輩社員に質問を聞く機会の2つが用意されるかと思います。
その際、相手にあわせて質問は選びましょう。
人事は会社全体の方向性やその雰囲気、制度については詳しいですが現場の仕事については知らないことが多いです。
反対に、先輩社員は現場については誰よりも詳しく、親身に教えてくださいます。
相手によって質問を使い分けて、適切な回答を得られるようにしましょう。
【20選】説明会・OB訪問の質問例
それではここから、研究職の職種理解におすすめの質問を列挙していきます!
研究テーマはどのように決定されますか?
上から降りてくるものを忠実に終わらせるトップダウン型なのか、現場から新たなテーマを生み出せるボトムアップ型なのかを区別できます。
自分が指事されたことをこなしたいタイプか、自分から見つけたことをこなしたいタイプなのかでその社風に適性があるのかを判別できますね。
研究成果を事業化するまでのプロセスを教えてください
研究成果が形になるまでの理解度を深められる質問です。
目の前の研究だけにとらわれず、その下流行程についての面接質問が来た際の対策に役立ちます。
1日の業務の流れを教えてください
社会人になれば院生とは違い、限られた時間、他の業務をしながら実験をすることになります。
入社した後のギャップをなくすため、1日の業務量や内容について正しく確認すべきです。
実際の残業時間もポイントですね。
研究職に求められるスキルや資質は何ですか?
面接でどのような強み弱みが使えるのかを確認できる質問です。
自分なりの「こういう人が資質があると思う」考えを聞けば、より具体的な対策になりますよ。
新卒が1年目から3年目までに行う仕事はどのようなものですか?
せっかく苦労して入社しても、約30%は3年以内に退職している現実があります1。
入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職を防ぐためにも3年以内にどんな仕事を行うのか知っておくことが大切です。
面接でもどんな仕事をするのか知っているのか、言葉の端々から見定められるため、確認しておくようにしましょう。
社外研究機関との連携や出向はありますか?
研究職のメリットの一つとして、転勤の少なさがありますよね。
しかし、社外の研究機関への出向によって、本来望んでいた勤務地から離れないといけない場合があります。
そうはいっても、外部研究機関と連携できるほどの研究力の高さも魅力的な企業の一因です。
具体的な頻度や出向の頻度、その機関の場所まで把握し、受け入れられるかどうかを確認しましょう。
企業研究とアカデミアの研究の違いは何ですか?
よく面接で聞かれがちな有名な質問です。
今までアカデミアで自由に研究をしてきた学生に、企業での利益を求められる研究との違いを問うてきます。
実際に働いている社員さんに聞けば、より具体的な内容を伴って答えやすいでしょう。

正直僕は聞かれたことない
学会発表や論文投稿の機会はありますか?
どのくらいのペースで発表の機会があるのか、筆頭論文は出しやすいのか、気になるところですよね。
特に、将来的にアカデミアに戻ってくることを考えている方々は業績のためにも重要です。
また、論文の執筆は外注できて実験だけやれば良いのか、そうではないのかも望む働き方の理解には重要ですね。
研究テーマには裁量権を持って携われますか?
アカデミアのように1人1テーマを責任持って携わるのか、手足となって実験だけするのかで随分やりがいは変わりますよね。
自分がどのような研究形態を望むのかはきちんと確認しておきましょう。
ビジネスモデルによって、実験内容すら指示されるのか、自社内で全て完結できるのかも大きく異なります。
業種の選択にも関わる要素ですね。
研究職のキャリアパスにはどのような選択肢がありますか?
入社直後だけではなく、将来自分がどのようなキャリアを選択して歩んで行けるのかも見通しておきたいですよね。
あらかじめ理想のキャリアを歩んでいるロールモデルが見つかっていれば、その企業での実現可能性は高いといえます。
会社によっては面接時に〇〇年後にどうなっていたいかを聞かれることもあるため、入念に対策をしておくと良いでしょう。

これはめっちゃ聞かれた!
研究職から別の職種にキャリアチェンジするならどのくらいの期間が必要ですか?
会社によって、ジョブローテーションが強制的に発生するのか、名ばかりなのか、手をあげないと異動ができないのかは実は異なっています。
人事は望めば異動できるといっていても、実際は難しかったりなんてことも。
研究職にこだわりがなく、その先は違う仕事もしてみたいと思っていたら聞いておきましょう。
研究成果が出てからどの工程まで携わりますか?
大企業になる程、業務が細分化され自分が携わる範囲が狭くなっている傾向にあります。
反対に、小さいほど研究から製品化まで横断して携わるようになりがちです。
自分がやりがいを感じるのがどこまでの範囲か、価値観と照らし合わせてみましょう。
開発部門や他部署との連携の仕事と実験の比率は?
研究職といえど、1人で実験ばかりやっているわけではありません。
他部署と連携をとって行う仕事もたくさんあります。
研究に没頭できる時間がどのくらい確保できるのかも重要です。
研究テーマの変更や新規プロジェクトの参加はどのように決まりますか?
企業では利益を得られる研究成果が重視される傾向にあります。
そのため、アカデミア以上にテーマ変更に流動性があることも。
特に一つのことを継続してやっていきたいタイプの人の場合、合わない環境かもしれません。
どんなスパンで新しいテーマに取り組めるのか聞いてみましょう。
研究成果が評価される基準や指標は?
営業と違って、研究って定量的に評価できない世界ですよね。
ところが社会に出ると仕事の成果によってお給料が明確に異なってしまいます。
研究成果はすべからく素晴らしいものとはいえ、どんなポイントが社内で評価されるのかは把握しておきましょう。
自分のモチベーションの維持にも繋がりますからね。
AIやデータサイエンスを活用した研究への取り組みはありますか?
その企業のアンテナや時代に合わせた流動性を持つかどうかを測れる質問です。
近年ではAIやビッグデータを活用したターゲット分子であったり、構造の探索が脚光を浴びています。
今後あたりまえになる分野にどのくらい投資できているのか、会社の未来を測れそうですね。
研究に失敗した時や難航した際の対応は?
部門の人柄を知れるかもしれない、そんな質問です。
研究をする中で絶対に行き詰まる時ってきますよね。
そんな時、定期的にメンバーと相談できる機会があれば、新卒でも働きやすそうではありませんか?
自分で何とかしなければいけない雰囲気なのか、覚悟しておけるだけでも違いますね。
在宅勤務はどのくらいできますか?
ワークライフバランスも大切にしていきたいところです。
研究職の大多数はオンサイトで働く必要があります。
でも実際は、実験は研究所でやるが、事務作業は在宅もOKな企業もちらほら。
家で仕事できるに越したことはないですよね。
企業の成長戦略の中で、研究職が果たす役割は何ですか?
会社にどう自分が貢献できるかというような、面接の質問に答えやすくなります。
どの企業も独自の成長戦略を打ち出すことで、さらなる利益の増進を図っています。
そんな中で、研究職としてどうやって貢献していけるのか、アカデミアと違った視点を持って就活できているのかを問われる時がくるかもしれません。
研究にかけられる予算や設備の充実度について教えてください
できるだけ予算が潤沢で自由に設備が使えるところに勤めたいですよね。
なるべく先輩社員に直接聞いておきましょう。
人事の方だと、現場の実験設備の不具合等については把握できていない可能性があります。
まとめ
いかがでしたか?
就活の質問をする機会って幾度もある上に、毎回考えるのって大変ですよね。
本質問集が皆様のお役に立てたら幸いです。